【Vol.1】万博はなぜ6ヶ月で終わる?その理由と種類を知ろう
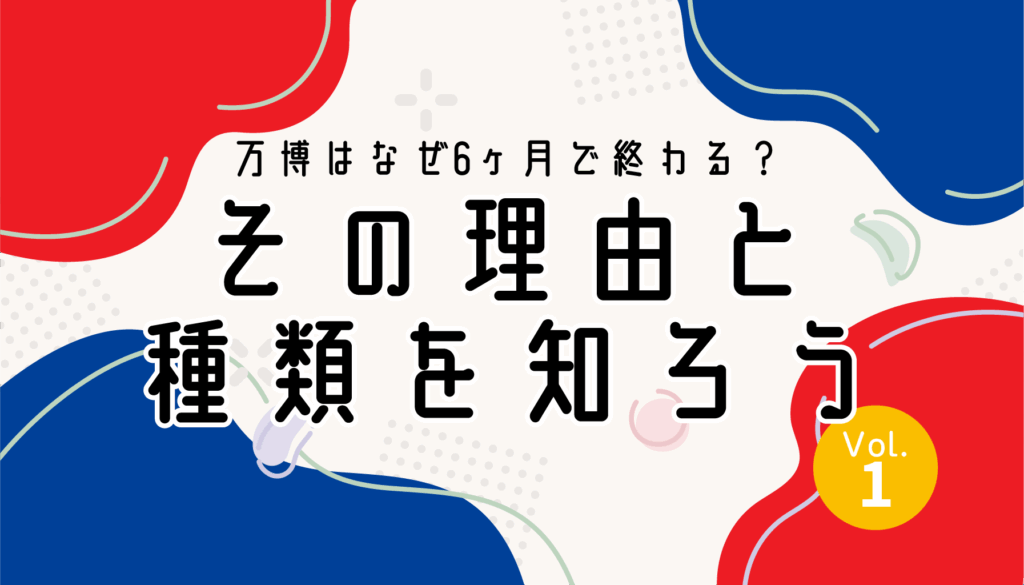
◆万博の種類を知ろう ― 登録博と特別博の違い
大阪・関西万博が閉幕しました。
半年間にわたって繰り広げられた熱気と感動がひと段落し、いわゆる“万博ロス”を感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、「そもそも万博ってどういう仕組みなの?」と疑問を持った方もいらっしゃるかもしれません。
実は、万博には国際的なルールがあり、大きく分けて2種類の形式が存在します。
それが「登録博(一般博)」と「特別博(専門博)」です。
「登録博」と「特別博」――聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は万博の種類を理解するうえでとても重要なキーワードです。
ここからは、それぞれの万博がどんなものなのか、わかりやすくご紹介していきます。
登録博(Registered Expo)
5年に一度しか開催できない、世界最大級の博覧会です。
テーマは広く、参加国が自国のパビリオンを自由に建設できるのが特徴。
期間は最長6か月と定められています。
日本での開催例
- 1970年 大阪万博
- 2005年 愛・地球博
- 2025年 大阪・関西万博
登録博は「技術・文化・人類の進歩」など、普遍的で壮大なテーマを扱います。
特別博(Specialized Expo)
一方で、特定のテーマに焦点を当てた中規模の博覧会が「特別博」です。
期間は3週間から3か月程度。テーマは科学、海洋、園芸など専門性が高い内容です。
主催者が展示ブースを用意し、参加国はその枠を使って展示します。
日本での開催例
- 1975年 沖縄海洋博
- 1985年 つくば科学技術博
- 1990年 大阪花博
- 2027年 横浜花博
なぜ万博は6か月しか開催しないの?
万博の開催期間が「最長6か月」と決まっているのは、国際博覧会条約に基づくルールです。
長期開催にすると運営コストや展示維持の負担が大きくなり、参加国にも影響が及ぶためです。
また、半年という期間は「技術と文化の最新を世界に示すのに最も効果的な長さ」とも言われています。
つまり、6か月は「世界を動かす展示の旬」なのです。
まとめ:万博は形を変えても“人と世界をつなぐ場”
登録博は「人類規模のテーマ」、特別博は「特定の課題への挑戦」。
どちらも世界が協力し、学び合うための舞台です。
次回【Vol.2】では、日本で実際に開催されたすべての万博を時系列で振り返り、
それぞれが残した“レガシー(遺産)”をたどっていきます。
