【合格者が語る、体験記】受験するなら知っておきたい!屋外広告士試験の攻略ポイントまとめ【前編】
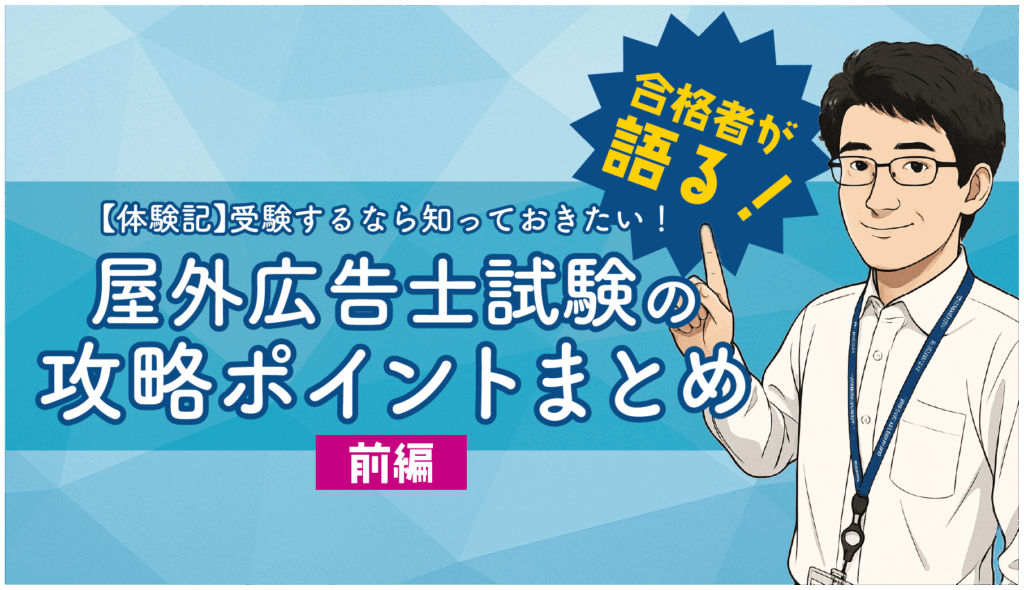
屋外広告の分野で働いていると、ある日ふと耳にするのが「屋外広告士」という専門資格です。この資格は、屋外広告物法や景観条例といった関係法規に基づき、適正な知識とスキルを持つことを証明するものです。
弊社が取り扱う電柱広告を始めとした、屋外広告に携わる業務において「業務主任者」や「管理的立場」となるための条件にもなっています。
私自身も、初めてこの資格の存在を知ったときは、「いつか取得しないといけないのかな……」という程度の認識でした。しかし、仕事を続けるうちにその必要性や重要性を感じるようになり、ある日ついに受験を決断しました。
実際に屋外広告士試験にチャレンジしてわかったのは、「しっかりと対策をすれば、決して難関ではない」ということです。もちろん簡単とは言いませんが、正しい勉強法で取り組めば、初心者や未経験者でも十分に合格を狙えます。
これから屋外広告士試験に挑む方のために、実際に体験した立場から、試験勉強の進め方や心構えをまとめてみました。これから学習をスタートする方にとって、効率的な学習方法やモチベーション維持のヒントになれば嬉しいです。
屋外広告士試験の内容とは?
屋外広告士の試験は、1日で完結する形式で、「学科試験」と「実技試験」に分かれています。
学科試験(3科目・必須)
- 関係法規
屋外広告物法・景観法・建築基準法など、法律に関する基本知識が問われます。- 設計・施工
看板・広告物の構造、安全性、材料、施工方法、道具の扱いなど技術的スキルが出題されます。- デザイン
色彩理論、光の使い方、フォント、視認性、広告デザインの歴史などデザイン理論を中心に出題されます。実技試験(いずれか1つを選択)
- 設計実技:指定された構造物に対する設計図を作成
- デザイン実技:与えられた条件を満たす広告デザインを制作
私は芸術系大学出身ということもあり、「デザイン実技」を選びました。自分の得意分野や過去の経験を基準に選ぶのがポイントだと感じます。
勉強を始めたときの正直な気持ちと、工夫したマインドセット
受験を決めた直後、実はモチベーションはほとんどゼロに近い状態でした。 「試験は難しそう」「勉強は大変そう」と感じていて、正直、申し込んだ時点で達成感を得てしまっていた部分もありました。
それでも、受験料が安くはないこともあり、「どうせ受けるなら後悔しないようにしよう」と気持ちを切り替える必要があると感じました。そこで私が最初に行ったのが、学習に対する意識の転換です。
具体的には、「勉強=楽しいこと」「屋外広告士の試験=意外とやさしい」と、あえて前向きな認識を意識的に脳に刷り込むようにしました。「マインドセット」という言葉にはやや抵抗がありましたが、「できない」「無理」と思ってしまうより、「楽勝かも」「楽しめそう」と考えた方が、結果的に行動につながると感じたのです。
勉強をポジティブに進めるための2つの工夫
私が特に意識していたのは、以下の2点です。
- 勉強中は、できるだけポジティブな感情で取り組む
過去問を解くときは、声に出してツッコミを入れてみたり、「へえ、なるほど!」と自分で反応していました。勉強に遊び心を取り入れることで、単調になりがちな学習時間に少し楽しさが加わります。- 「この試験は難しくない」と思い込む
専門用語に出くわすと、「わからない=難しい」と感じがちですが、私は「ただ知らないだけで、内容はそこまで複雑じゃない」と考えるようにしていました。- 実際、意味を調べてみると「意外と当たり前のことだった」と思うケースが多く、用語の壁を越えるだけで理解が一気に進むと実感しました。
勉強を苦しくしすぎず、ポジティブな気持ちを維持することで、自然と学習習慣が身につきました。 これから勉強を始める方も、まずは自分なりのモチベーションの上げ方を見つけることで、スムーズに学習を始められるはずです。
Vol.2では、もう少し具体的な勉強方法をまとめていきます。
